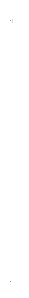
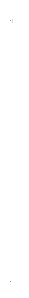
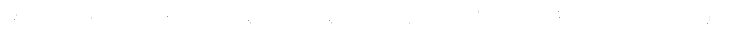

































































































































































































































































































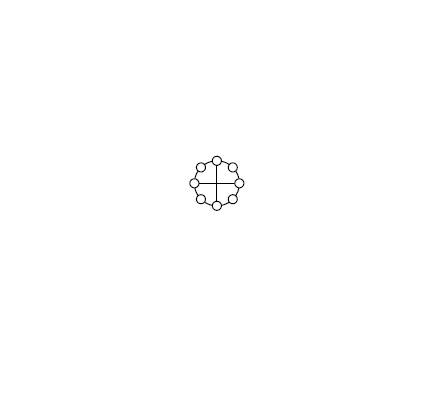


ワ
ラ
ヤ
マ
ハ
ナ
タ
サ
カ
ア
ヰ
リ
ヰ
ミ
ヒ
ニ
チ
シ
キ
イ
ウ
ル
ユ
ム
フ
ヌ
ツ
ス
ク
ウ
ヱ
レ
ヱ
メ
ヘ
ネ
テ
セ
ケ
エ
ヲ
ロ
ヨ
モ
ホ
ノ
ト
ソ
コ
オ
ン
カタカムナは、上古代 (何千年〜何万年前とも言われる) に日本列島に存在したとされるアシア族の
文明の呼び名です。 彼らの用いていた文字をカタカムナ文字、文献を「カタカムナ文献」と呼びます。
その文献は、八鏡文字(はっきょうもじ)と呼ばれる大小の ○ ・ 直線 ・ 半円 ・ 四半円を組み合わせて
イロハ48音を表し中心から外側に向って螺旋状に並べ、内側から外側に読むことに特徴があります。
「 ウィキペディア 」 より転載
「カタカムナ文明」 縄文時代以前、旧石器時代末期に存在したとされる。
極めて高度な科学技術や独自の哲学体系を持っていたことが、神代文字で記された文献から推測されるが、
この文明の存在を示す遺構や遺物は、この文献以外は見つかっておらず、原本の所在も不明である ・ ・ ・・
日本で初めてカタカムナ文明の存在を唱えたのは楢崎皐月である。 楢崎は古事記や日本書紀等を参考に、
5年をかけて 「カタカムナ文献」 の解読に成功。 その内容が自然科学的な実用書であった事を突きとめた。